エンジニアは「AI が言っていました」と説明しない習慣を身につけるべき
カテゴリ: 生成AI
記事投稿日: 2025年5月24日
記事更新日: 2025年9月22日
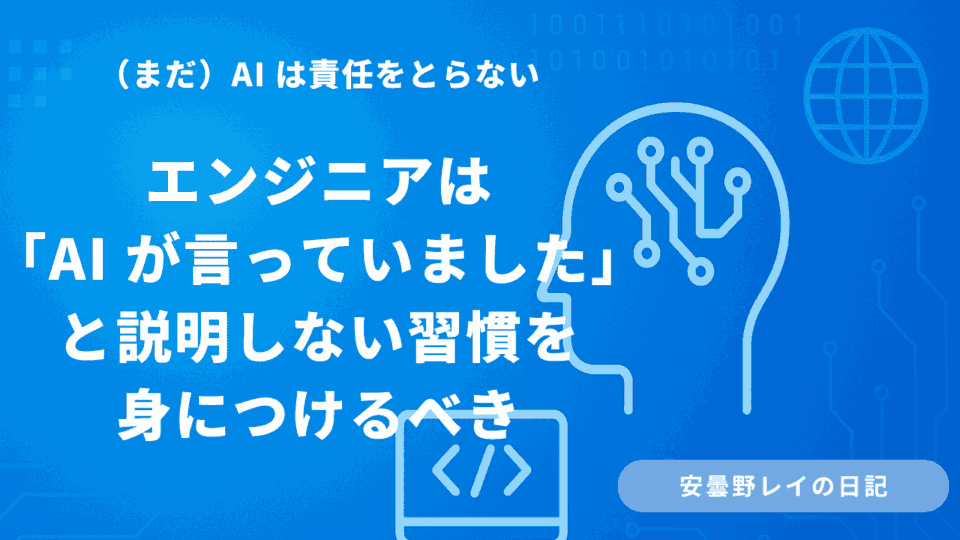
(まだ)AI は責任をとらない
仕事で生成 AI のサービスについて語る機会が増えてきました。
当初から「生成 AI が◯◯と言った」「生成 AI に聞いたところ~」という説明は意味がない、という話をしてきました。
生成 AI は『何も責任を負わない』からです。
少し前に、説明用の動画を作りました。
生成 AI は「最先端」のツールかもしれませんが、道具としては『「文章の続き」を高確率で生成しているだけの機械』です。
▼ 「文章の続き」を作る AI・生成AI入門 第1回 【5分で理解シリーズ】
その道具は磨かれているか
生成 AI が◯◯と言った、という説明はしないほうがいい、意味がないから、という説明は、しばらく経つと、忘れられることが分かってきました。
それだけ、生成 AI のことを信用し、生成 AI をよく使うようになってきた、ということなのかもしれません。
でも、どんなに賢くなってもそれは「新聞や雑誌で◯◯と言っていた」とか「検索エンジンで調べたところ~」と言っているのと大差ありません。
なにかの情報について語る時、話す人は、それについて責任を負う必要があります。
大げさな、と思うでしょうか。
情報は両刃の剣です。
便利な反面、時には判断を誤らせます。
人生や社会にとって、取り返しのつかないことをさせる材料になりかねません。
偽の情報を流布させれば、政治や戦争を動かせることは、大国の歴史を見れば明らかです。
私は単純に、どんなツールも使う人次第だと常に思っています。
「いろんな道具を出しても使うのは人間だからね」(大長編ドラえもん「のび太の宇宙小戦争」より)
この言葉を私はよく引用しますし、しょっちゅう思い出します。
道具を使うのは人間で、その責任は常に人の側にあると思っているからです。
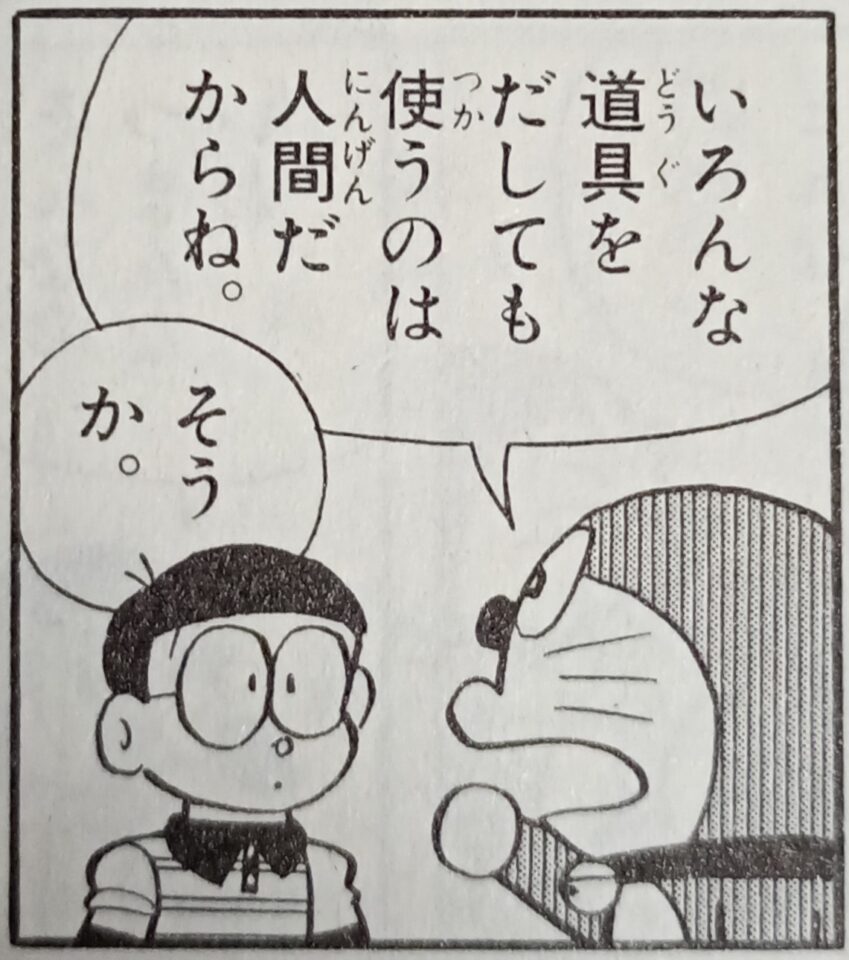
いろんな道具を出しても使うのは人間だからね(ドラえもん)
ドラえもんでは、のび太がよく、間違った道具の使い方をしてオチがつきます。
そのたびに、のび太は「ろくな道具を出さないから悪いんだ」と怒り、ドラえもんも「道具のせいにするな」と反撃します。
まったく、ドラえもんのいうことは正論です。
生成 AI は(まだ)「高確率で賢い答え」を言っているのに過ぎず、100% の保証は常にありません。
確かめるのは人間の責任です。道具を使う人間が、その結果を背負うというだけで、何も特別なことはありません。
生成 AI を包丁にたとえてみます。
それは食材を本当によく切れるように、手をかけて(プロントに注意して)、自分の手を切ったりしないよう注意深く(情報の引用元や内容を確認して)、使っているでしょうか。
よく手入れされた道具は、プロンプトの達人を見ているといつも圧倒されますが、驚くような成果を見せます。
逆に悪用すれば、道具は人を傷つけ、社会まで壊してしまいます。便利なものほど、そうなのです。
『マッチ1本、火事のもと』なのです(若い人はマッチなど知らないかも…?)。
簡単に使える分、その線引きを認識していなければ、やがては道具の理解をしていない、あの人は「危うい人」だと言われてしまいます。
まして、エンジニアや、技術にたずさわる人は、よくよく言動に注意しないといけません。
道具に慣れるほど、扱いは雑に、おろそかになりがちです。
が、エンジニアはそれではいけないと思います。

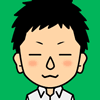

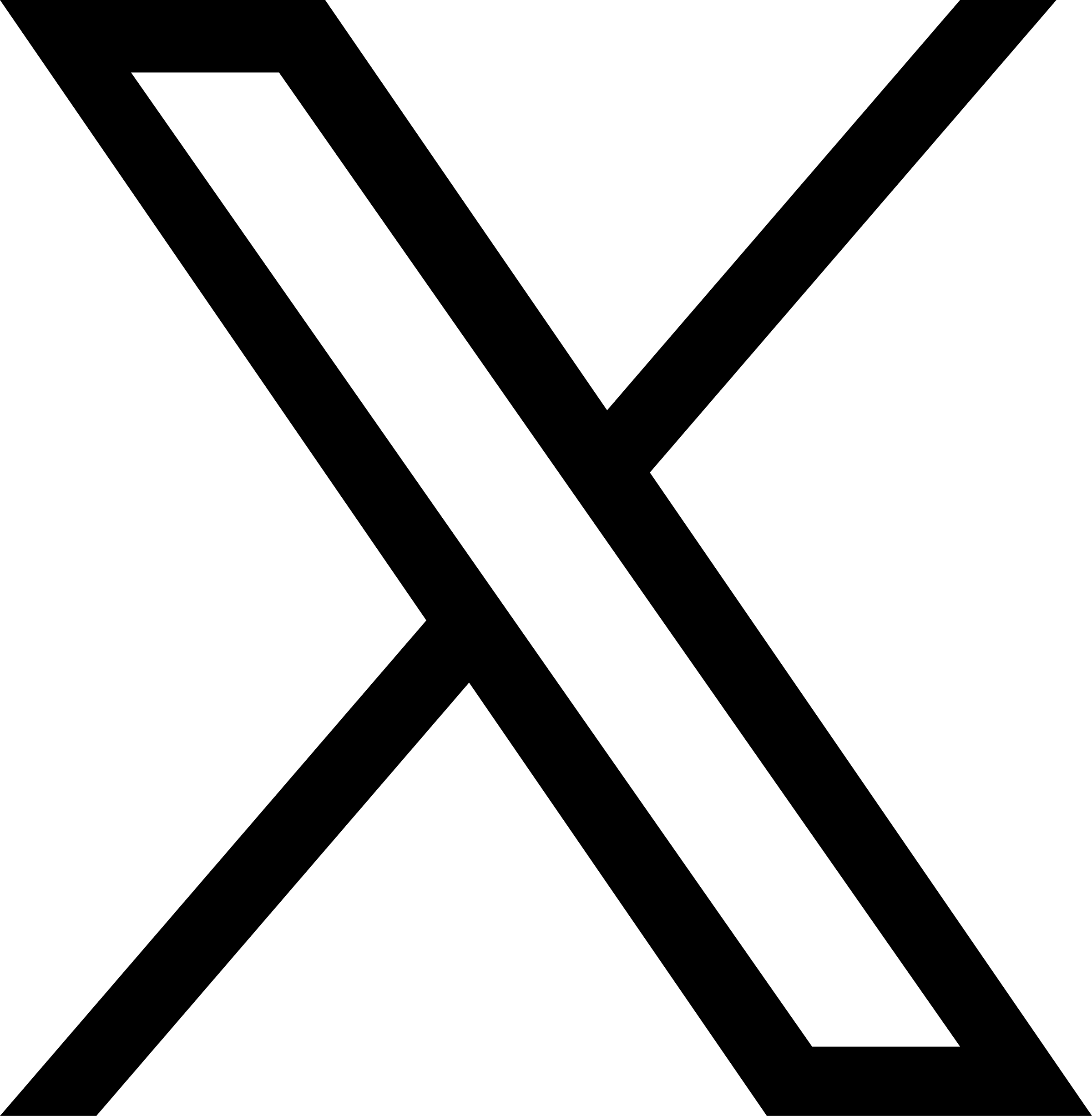
コメントを残す